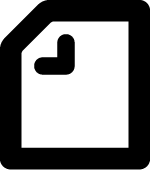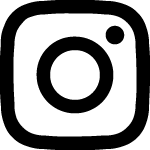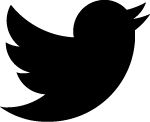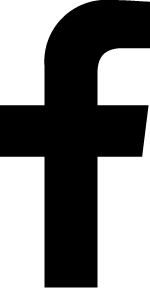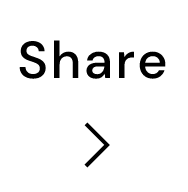撮影:原 祥子
公園に、地域に、資源が“くるり”と巡り、還る。京都音楽博覧会と探る、イベントの未来
撮影:原 祥子
京都音博を開催するにあたり「地域や会場である梅小路公園へ還元できることを」という思いから、2022年度より「資源が“くるり”プロジェクト(以下、資源が“くるり”)」をスタート。当日会場で出た食品残さをコンポストで堆肥化し、公園内の花壇に循環させる取組から始まり、3年目となる2024年度は、京都市内7事業者によるさまざまなブースが展開。プロジェクトの広がりも感じる2日間となりました。
今回は、くるりの岸田繁さん、梅小路まちづくりラボの足立毅さん、サーキュラーエコノミー専門家の安居昭博さん、株式会社キョードーグループ代表取締役の内田幹二さんと、京都音博に深く関わる4名に集まっていただき、3年間での変遷や、これからについて語っていただきました。
音楽と、循環と。京都音博にさまざまに関わる

−−まずは改めて、自己紹介をいただけますか。
岸田繁さん(以下、岸田さん) はい、岸田です。くるりというバンドをやっています。ミュージシャンです。よろしくお願いします。

足立毅さん(以下、足立さん) 足立です。京都リサーチパークで働いています。この5年ほどは、京都音博の会場もある梅小路エリアのまちづくりを担う、梅小路まちづくりラボという会社を地域の方と運営しています。そこでの活動が縁となり、京都音博とのコラボも始まりました。

内田幹二さん(以下、内田さん) 内田です。大阪でコンサートプロモーターをしており、関西を中心にコンサートや舞台、スポーツイベントの企画や運営をしています。京都音博は2019年度から関わっています。

安居昭博さん(以下、安居さん) 安居です。3年ほど前に足立さんからお声がけいただき、京都音博の「資源が“くるり”」のアドバイザーとして関っています。普段はサーキュラーエコノミーという資源循環の仕組みづくりを専門にしており、京都市の成長戦略推進アドバイザーにも就任しています。サーキュラーエコノミーが進められているオランダとドイツに住んでいた経験を活かし、いろいろな方と関わらせていただきながら、日本に合った仕組みづくりを行なっています。

−−ありがとうございます。京都音博は2024年で18回目を迎えられましたが、今回掲げられていたテーマや、印象的なことがあればぜひ教えてください。
岸田さん やっぱり音楽イベントなので、ブッキングで“色”が決まります。そこが毎回苦労する部分でもありますが、京都音博にしかないものをつくろうと常に意識しています。今年度テーマに掲げていたのは、とにかく音楽のジャンルを”壊す”ということ。そう聞くと怖い印象を与えるかもしれませんが、普段行かないコンサートや、知っているけど見たことがない演奏を見ることができる機会にしたいと思っていました。今回はイタリアのミュージシャンを招聘したり、オペラや声楽の世界で活躍されている方を見られる機会をつくったり。いわゆる音楽フェスに出ない人たちを中心に出演していただきました。

足立さん 今年度の京都音博で印象的だったのは、ASKAさんの名曲のイントロが聴こえてきた瞬間。僕らはボランティアのみなさんとリヤカーを引きながら、会場内のエコステーションをまわって食品残さを回収するんですが、回収しながら聴こえた時は、気持ちが沸き立つようでした。でも、一緒にいたボランティアの学生がポカンとしてて(笑)。「わからへん?」って聞いたら「サビだけは知ってます。いい曲ですね」と。これが音博のマジックやなっていう瞬間に立ち会えて、面白かったですね。
 ボランティアで参加するメンバーは、地元の方から大学生までさまざま
ボランティアで参加するメンバーは、地元の方から大学生までさまざま
 アーティストの創作活動から生まれる資材を再循環させる『副産物産店』プロジェクト
アーティストの創作活動から生まれる資材を再循環させる『副産物産店』プロジェクト
安居さん 私が関わるのは3回目ですが、「資源が“くるり”」をもともと知って来られた方が過去2回に比べると多かったように感じます。たとえば袋いっぱいに古着を詰め込んで持ってこられる方や、京都芸術大学で出た古材を提供するブースでは、お子様連れのご家族が集まって楽しそうに古材を手にされる姿が見られるなど、本当にさまざまなかたちで資源循環のコンテンツを楽しんでおられたのが印象的でした。
この場所にあったやり方で、地域に還元する

−−「資源が“くるり”」の始まりは2022年。初年度から3年の間で、どのように変遷してきたのでしょうか?
足立さん コロナ禍でオンライン開催となっていた京都音博を3年ぶりに梅小路公園で開催すると決まった時、岸田さんと何か新しい取組ができないかと意見交換をさせていただいたことがきっかけです。その中に、京都音博にはたくさんのフード店が出店されるので、そこから出る食品残さを回収して、梅小路公園に堆肥コンポストを設営し、できた堆肥を公園の花壇などに使えると面白いんじゃないか、というアイデアがありました。振り返ると、京都音博自体が環境に配慮された音楽フェスで、紙のパンフレットをつくらないとか、100%リユース食器にするなど、親和性があったんです。そこで2022年にコンポストを設営するところから始めさせていただきました。同時に、当日の地域の事業者さんと一緒に何かブース展開しようと考え始めた取組も、今年度は7団体にまで広がりました。京都で資源循環に関する事業や取組をされている事業者さんが出店しているイベントという特徴もできあがっています。

今回ブース展開された事業者のみなさま。サステナブルなコーヒーのあり方を追求する『小川珈琲』さんや、衣料から肥料をつくるという画期的なシステムを持つ『ピエクレックス』さんなど、それぞれのアプローチで資源を“くるり”と循環させるためのチャレンジを行っています!
−−先ほど紹介があった古着の回収や古材の提供のほか、電力を一切使用せず自転車のペダルを漕ぐだけでミックスジュースをつくるマシンの体験、生八ッ橋の耳や酒かすといった京都のまちから出るロス食材を活用したシュトレンが販売されるなど、広がりをすごく感じました。岸田さんは、今年度の「資源が“くるり”」をどう見られましたか?
岸田さん やっぱり足立さんと安居さんの熱量のすごさでしょうか。アイデア自体も素晴らしいですし、それを継続していくことでじわじわと周知されていると感じます。

岸田さん そもそも音楽イベントは、運営がすごく大変なんです。本当は会場を閉め切って、音が漏れないようにできると一番ありがたいんですが、京都音博ではそうはせず公園を使わせていただいています。そのため、地域の方々になにか少しでも返せたらという思いから、いろいろなことが始まりました。実現できなかった試みもたくさんありますが、「資源が“くるり”」に関してはアイデアと熱量が本当に素晴らしいので、継続的に続けばいいなと思っています。

電力を使わずミックスジュースがつくれる『MIX BIKE』。この自転車自体も古いエアロバイクをアップサイクルしてつくられているそう

京都で発生する副産物や規格外品を主原料にした八方良菓の「京シュトレン」
−−内田さんはプロモーターという立場上、たくさんの音楽イベントに関わられていると思いますが、その視点から感じられる京都音博ならではの特別さを教えていただけますか。
内田さん 京都音博の初開催は、全国各地で音楽フェスが始まりつつあった頃だったと思います。当時からほかのフェスにはまったくなかったような視点で行われており、まさに「音楽の博覧会」を目指してスタートされたのかな、と横から見ながら感じてきました。それを18年間ずっとやってこられている、というのが音楽業界で見ても異質ですよね。突出しているような印象です。そもそも、まったく違う視点でキャスティングがされており、くるりならではの特色だと思います。放送局やイベンターが始めたフェスはたくさんありますが、アーティスト自身が音頭をとって主催されるケースはほとんどなかったと思います。その流れの中で「資源が“くるり”」も始まり、ほかのフェスにはない新しいことをさらにスタートされたのかな、と感じていました。

−−「資源が“くるり”」のような、環境に対するアプローチをされている音楽イベントはほかにあるのでしょうか?
内田さん 珍しいんじゃないかなと思います。リユースカップやごみの分別を徹底されているフェスはたくさんありますが、それ以外のことに取り組まれているのは京都音博ならではかなと。
岸田さん 場所が大事なポイントだと思っていて。梅小路公園は、市内各地にある児童公園のような公共の公園ともまた違った公園です。丁寧に管理された植栽があり、都心に近い。京都音博を始めた頃、まだこのあたりは閑散としていた印象があったんですが、その後、水族館や鉄道博物館、駅などがつくられ、その発展を見てきました。

岸田さん 公園自体も新しくて、できたのが1995年とかですよね。京都には古いものがたくさんありますが、ここは比較的新しい場所です。こうした公園の変遷も見てきたので、愛着もあります。そんな中、「資源が“くるり”」ではコンポストに取り組んでいますが、もともと自然だった場所に自然環境をつくるっていう逆AIみたいな不思議なことをやってらっしゃって(一同笑い)

岸田さん 生活していたら不要なものは出ます。そのこと自体は、別に悪いことじゃないと思いますが、梅小路公園を使わせていただいているので。環境を大事にしていますと言うんじゃなくて、この場所に似合うやり方でできたらと思います。
「資源が“くるり”」で生まれたコミュニティ

足立さん 今日は昨年度の京都音博の食品残さからつくった完熟堆肥を持ってきました。実際に今、公園の花壇に関わる市民団体さんが使われています。梅小路公園にある落ち葉を使うことで、その葉にある菌が活性化し、発酵するんですよ。4ヶ月ぐらいかけて、ボランティアのみなさんと水分を足したり、かき混ぜたりして、完全に堆肥になっていく。そういう過程を皆さんと楽しみながらやっています。


−−梅小路公園の植物があるからこそできるコンポストなんですね。
足立さん そうです。食品残さだけでは肥料にならないんですけど、梅小路公園の落ち葉や、大原の籾殻、伏見の酒屋さんの米ぬかや、伏見の瓦屋さんの瓦土とかをちょっとずつ足しながら発酵させていきます。
安居さん 京都音博は2日間の開催ですが、私たちはこの日をめがけて大原の農家さんのところをまわり、準備をしています。開催当日も、堆肥化しやすいように食品残さを水気を切った状態で回収できるよう出店者の方々にザルとバケツをお配りしたり。これも3年間の発展があったからこそできたことですね。



安居さん 堆肥は4ヶ月ほどでできあがりますが、その間も放っておくのではなく、足立さんを中心にさまざまな人が切り返しという作業に関わっています。和束町という最南端地域から来られたり、大学生が参加されたり。最近、私自身のテーマとしても「手入れ」が肝心だなと感じているところがあるんです。多くの人々が手を入れることからこそ、質のいい堆肥ができたり、梅小路公園ができたりするんですよね。ところで、切り返し作業には毎回何名が関わっていらっしゃるんですか?
足立さん 毎回10〜20人ぐらい来てくれますね。初年度は人が集まるか本当に不安でしたが、実際にやってみると関わりたい人は世代関係なくいらっしゃって助かっています。

安居さん 先日足立さんから伺ってすごくいいなと思ったことがあるんです。京都に「AWAKE LEMONADE」というレモネード専門店を営む事業者さんがいらっしゃるんですが、その方が切り返しの場にレモネードを持ち寄られたそうなんですね。作業をした後にみんなでレモネードを飲まれたそうで、今までつながりのなかった方々がこの場を通してつながったんだなと感じました。切り返しという定期的に会う場面があること自体、京都音博のアフタートークのような感じかもしれません。開催後もコミュニティの取組として続いていることが、この3年間で見えるかなと思います。
足立さん コンポスト作業よりレモネードタイムのほうが長くて(笑)。みんなでしゃべってるだけなんですけど、それがすごくいいんです。
京都の中で循環する

−−昨年度より「資源が“くるり”」ブースでは、古着の回収も行われていますね。
足立さん 京都は昔から古着屋さんが多い街ですが、「SPINNS」という古着屋を経営されるヒューマンフォーラムさんらと一緒に、梅小路公園にて春と秋に「循環フェス」というイベントを開催しています。そうした関わりの中で彼らと京都音博でもコラボできないかと考え、昨年度より古着の回収ボックスを置き始めました。京都音博のWebサイトでそのことを告知すると、みなさん古着を持ってきてくださったんです。古着の中には使えるものも多いので、それを販売されたりリメイクされたりすると聞いています。自分たちのいらないものを誰かのほしいものに変えていく、これも「資源が“くるり”」だなと感じています。単に箱にポンと入れて終わりじゃなく、会話も生まれています。話してみると、2年連続で古着を持ってこられた方だとわかったり。「資源が“くるり”」ブース全体で見ても、今年度は来場者との会話が多かったのも印象的でした。

 家庭で不要になった使用済みの衣服を回収し再活用の輪を広げる『RELEASE⇔CATCH』プロジェクト
家庭で不要になった使用済みの衣服を回収し再活用の輪を広げる『RELEASE⇔CATCH』プロジェクト
安居さん 「資源が“くるり”」と同時期に、京都市内でも古着回収ボックスの設置を始められましたよね。京都信用金庫全店舗や、市立高校全校に設置されるなど取り組みが広がっています。いらないものはフリマサイトで販売するなどいろいろな方法がありますが、この古着回収ボックスに持っていくと、人と人の温かさのようなもを感じられる方も多いと思うんです。なかなか言葉で表すのが難しいですが、だからこそ持ってこられる方が多いんじゃないかな、と。
私自身も中高生の時に古着を着ていましたが、当時と今の古着って少し違うところがあると思っていて。世界的な統計でも、この20年間で私たちが持っている服の数は平均で大体倍になっているんです。服の所有数が倍になると、1点あたりの着られる回数が明らかに減ります。状態の良いものもたくさんあるので捨てるのも忍びなく、できれば地域の方々に使っていただきたいという思いが生まれるのもわかります。今、さまざまなブランドやお店で古着回収をされていますが、海外に送られたり、繊維になったりするものも多い。京都市でのこの取組は、地域に暮らす方々にまた着てもらえるので、一般的な資源回収の仕組みとはちょっと違う循環ではないでしょうか。

−−「資源が“くるり”」を行うことで、京都音博がまちの循環の大きなハブになりつつあるように感じました。岸田さんは、京都音博でこうした取組を続ける意義をどのように感じていらっしゃいますか?
岸田さん 普段は自由に入れる、犬の散歩をされているような場所を閉め切って公演させていただいているので、こちらとしては申し訳ないんです。いわゆる対価交換は難しいですが、まず京都音博に来ていただいた方には音楽でお返しする。開催にご協力いただいている地域の方々にも、京都音博があるからできたことを残していきたい。私は「資源が“くるり”」に関しては、本当に何もしていないんですよ。足立さん、安居さんのアイデアを聞いて面白いなと思うぐらい。まずは京都音博をしっかりつくって、自分たちは演奏して、お客さんに届けることが仕事なので。
安居さん 京都駅から歩ける距離にこれだけいい公園があるのに、実は行ったことがない市民の方も多いと感じていて。そうした方々が、京都音博をきっかけにはじめて梅小路公園にやって来られることも本当に多いですよね。知ることでその後も散歩したり、子どもを連れて来られたり、周辺の街歩きをされたり。「資源が“くるり”」の来場者の中にも、はじめて来られたという方がいらっしゃるので、来ていただくことで地域や公園の魅力を感じていただくという点でも、方向性は一緒なのかなと感じます。
続ける、伝える、広げる

−−最後になりますが、京都音博と「資源が“くるり”」の今後の展望をお伺いしたいです。
内田さん やはりほかの音楽イベントにはないものが多いので「京都音博でやっているあれをうちでもやりたいな」というふうに、広がっていくといいですよね。フェスの新しい形を提示できるといいなと感じます。

安居さん 実は初年度の「資源が“くるり”」の後に、愛知の蒲郡で毎年開催されている「森、道、市場」の代表の方から、ぜひうちでもこうした取組をやりたいと声をかけていただき、3年前から関わらせていただいているんです。環境のためにという視点ももちろんあると思うんですが、それをやることによって地域に何か残せたり、音楽イベント自体の楽しみ方として新たな形が提示できたりと、さまざまな可能性を感じていただけているのかな、と個人的には感じています。
足立さん 2026年度で京都音博は20周年ですよね。この年は「資源が“くるり”」にとっても5周年目にあたるんです。この5年間の積み重ねの中で、地域とのコラボレーションができたらいいなと思っています。そして20周年の時に、もっと素敵な関係性になっていたらいいな、そこに近づいているのではないかなと感じます。

安居さん 岸田さんは、20周年に対しどういう思いを持たれていますか?
岸田さん その年、その年でしかないですね。単純にこの規模のイベントを毎年続けていくだけでもすごく大変。さらに、ずっとやっているとだんだん慣れてくるから、しょうもないものになってしまうこともあると思うんですよ。僕らはアーティストとして、しょうもなくならないようにすることが大事なテーマで、過去と同じことをやってても仕方がない。

岸田さん もちろん周年的なこともありますが、周年じゃない年に手を抜くことにもなっちゃうので、さほど意識していなくて。私としては、今は市内のホテルも予約が取りづらいですし、近畿地方のお客さんにたくさん来ていただけるように頑張らないとなという気持ちです。地元の方が行きたいと思って来てくれる、そういうものを目指していかないとなと思います。

−−音楽イベントのみならず、人の出入りの多い大きな催しでは、ごみが出る、交通量が増えるなど、どうしても環境に負荷がかかることは避けられません。それらにどうアプローチできるのか模索することは、これから先の未来も持続可能なイベントにするためにも不可欠な視点ではないか、と感じます。みなさんは、「資源が“くるり”」を続けていくことが、京都音博そのものの持続性にどうつながっていくと思われますか?
足立さん 難しい質問ですね(笑)。岸田さんはアーティストなので、ご自身で環境問題に対することをおっしゃられないんですが、音博が始まった頃からさまざまな取組を自然とされていました。参加者にも毎年マイ食器を持って来られる方もいて。最近はそうしたこともトレンドになっていますが、18年前からって早いですよね。一方僕らは地域の方と直接関わりながら「京都音博は環境にもアプローチしているイベントなんですよ」とめちゃくちゃ言っています。ステージ上でメッセージされなくても、僕らが代わりに言う。これからはそういう役割分担もあるのかな、と思います。
安居さん 私はサーキュラーエコノミーを専門にしていますが、「サーキュラー(循環)」と「エコノミー(経済)」が結びついているからこそ面白いと感じています。環境への取組が経済性につながったり、収益を上げることにつながったりすることが大切だなと思うんです。私もぜひ内田さん、岸田さんにお尋ねしたいんですが、「資源が“くるり”」の取組が、京都音博の存続性や持続可能性を考える時に必要な収益にどう接続できるのか、こういった形もあり得るんじゃないかなどご提案があれば伺いたいです。
岸田さん 「好きにやってください!」と投資していただくとか……。(一同笑い)
足立さん この活動に感銘した!みたいな感じでね。

内田さん もちろんそう思ってくれる人もいてほしいですが、まず京都音博や「資源が“くるり”」によって世の中が良くなるんじゃないかとか、人に対して優しくなれるんじゃないかと思ってくれる人たちが増えてほしいなと思いますね。それがビジネスにつながればなおいいと思いますが、すぐビジネスに、という話ではないと思いますので。ちょっとずつ広がっていけばいいですね。
岸田さん やっぱり長く続けてるものなので、その価値観をどれほどお客さんに理解していただくかが大切。ただワーってやり散らかしている音楽フェスじゃないんだよってことを、時間をかけてつくっていかないと伝わらないと思うので。実際にコンポストをやってみないとわからないこと、ステージを組んでみないとわからないこと、いろいろあります。多くの方に参加していただいているイベントなので、お客さんも含め参加していただいている方たちがいい瞬間をつくっていける場でありたいなと思っています。


京都音楽博覧会 × サーキュラーエコノミー
京都音博が環境のための取り組みとして新たにはじめたプロジェクト。その取り組みのひとつとして「食品由来の廃棄物から堆肥を作るための “コンポスト” 」を梅小路公園に設置。フードエリアで出る廃棄材料や食べ残しを堆肥に変え、公園内の花壇の肥料にする取り組みです。
「京都音博」を契機に、今後の環境について考える観光コンテンツにもなる「コンポスト・ステーション」への発展を目指しています。 資源が“くるり”プロジェクトの記事一覧へ >
編集者・ライター
このライターの記事一覧へ >