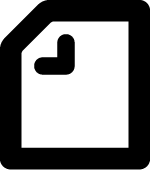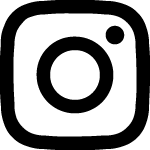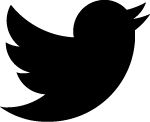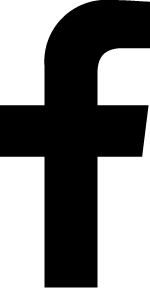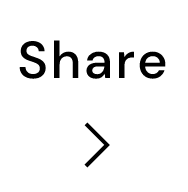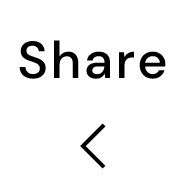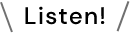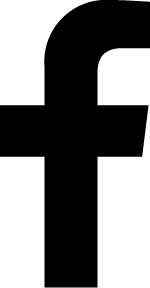インタビュー:徳谷 柿次郎
撮影:木村 華子
森見登美彦は“妄想の京都”で創作をする。鴨川デルタで回想する茶色の青春
インタビュー:徳谷 柿次郎
撮影:木村 華子
すでにあたりは藍色の夕闇に没している。鴨川デルタは大学生たちが占拠して賑やかである。新入生歓迎会の宴をやっているのであろう。思えば、そんなものにも無縁の二年間であった。
(『四畳半神話大系』角川文庫p281より)
空回りしながら青春を駆け抜ける大学生たちの煩悶や、妄想や、恋路や、物語の結末や、そうしたさまざまを受け止める森見作品の舞台のひとつが鴨川。特に、高野川と賀茂川が合流して鴨川となる逆三角形の場所、通称「鴨川デルタ」は森見氏のファンの間で「聖地」と呼ばれ、訪れる人も多くいます。
今年、小説家デビュー20周年を迎えた森見さん。なぜ、鴨川をはじめとした京都を舞台に小説を書き続けてきたのか。自身も大学生活を送った京都の景色にいま、何を思うのでしょうか? 鴨川でインタビューをおこないました。
原風景は「郊外の住宅街」

−−森見さんは京都のお隣・奈良の出身ですが、京都には元々どのようなイメージがあったのでしょう。
大学に入るまでは京都を強く意識したことはなかったですね。近すぎて学校行事でわざわざ行くようなこともなかった。京都も古都だけど、奈良も古都じゃないですか。その点、ちょっと対抗心はありますね(笑)。
ただ、僕の父が京都大学を出ていて、大学生活の破天荒なエピソードを聞かされてたんですよ。父が学生の頃は大学紛争の時代ですから、京大で半年授業がなかったとか、正門が封鎖されていて脇からしか入れなかったとか。
−−今と比べて、かなりダイナミックな。
荒っぽいというか、不思議な時代ですよね。夜になると大学の近所にラーメンの屋台が出没してた、って話もあったなあ。あとは「(京大は)面白いやつが多いよ」とも聞いていたので、「父親の通った大学に行ってみたい」という動機のほうが、大学を選ぶにあたって強かったかもしれません。
−−それでご自身も、京都の大学生に。
とはいえ最初の1〜2年は「奈良へ帰りたいな」と思ってましたよ。
−−それはなぜ?
京都のような長い歴史が積み重なった街に、うまく馴染めなかったんですよね。自分の生まれ育った奈良郊外の住宅地に比べて、圧倒的に情報量が多かった。京都の情報量が自分にとっては重たくて、「もっと何もない場所に行きたい」と。
奈良の郊外や大阪に住んでた頃の万博公園とか……ちょっと抽象的で空っぽな感じの世界が僕の中での原風景なんですよね。
−−歴史ある建物が密集している街よりも、ある種の人工的につくられたような街が原風景。森見さんの作品のイメージからすると、意外です。
 デビュー作『太陽の塔』をはじめ、初期から古都・京都を舞台にした作品が多くを占めている
デビュー作『太陽の塔』をはじめ、初期から古都・京都を舞台にした作品が多くを占めている
大学の4年間で書いていた小説は、郊外の住宅地が舞台だったんです。でも、全然うまく書けなくて悩んでました。
だけど近代文学のような昔の小説を読んでいたら、自分の中に古めかしい言葉が溜まってきて。その日本語をそのまま書くとリアリティがないけれど、京都で暮らしている、ちょっと時代錯誤な大学生の語りということにしたら、これがしっくりきたんです。
−−それがデビュー作の『太陽の塔』?
はい。だから、その7年ほどあとに書いた『ペンギン・ハイウェイ』は、いわばリベンジなんですよ。小説の技術がついてきて、SFのような別のモチーフを持ってくれば、郊外の住宅地が舞台でも書ける、とわかった結果でした。
 2010年に角川書店から刊行された『ペンギン・ハイウェイ』。第31回日本SF大賞受賞作。小学4年生の男子・アオヤマが住む「郊外の住宅地」に、ある日突然、ペンギンの群れが出現しはじめる。この事件に歯科医院のお姉さんが関わっていることを知ったアオヤマは、ひと夏をかけて不思議な謎に挑んでいく
2010年に角川書店から刊行された『ペンギン・ハイウェイ』。第31回日本SF大賞受賞作。小学4年生の男子・アオヤマが住む「郊外の住宅地」に、ある日突然、ペンギンの群れが出現しはじめる。この事件に歯科医院のお姉さんが関わっていることを知ったアオヤマは、ひと夏をかけて不思議な謎に挑んでいく
京都というお皿に、自分の妄想を載せている

−−森見さんの小説といえば「京都の大学生」のイメージだったので、「奈良の郊外」から創作がスタートしていたとは、とても意外でした。
僕としては大学時代の経験や身の回りにあった世界を舞台にしつつ、京都という街の素材を活用して、自分の妄想を書いているんです。なので、僕の小説に出てくるのがリアルな京都や京大生だと思われると、困ってしまうところがある。正直、悩ましいですね。
−−そんな葛藤が。
実際の京都での経験や景色も混ざっていて、まったくの嘘ではないんですけど……。サイン会で読者の方に「森見さんの本を読んで京都の大学に入りました」「京都で就職しました」と聞かされるたびに「うわあ!」と。年々、罪の意識が生まれてきて書きづらくなっています(笑)。

−−それだけ森見さんの「妄想」に引力があるんだと思います。たくさんの人を惹きつけるくらい、面白くて素敵な場所に、森見さんの描く京都が見えている。
僕は京都に対して、ずっと「学生」のつもりなんです。学生って、土着の人間ではなくて、何年かしたら出ていく存在じゃないですか。僕はその学生の期間が伸びて、いまで20年目くらいになっているんですが。京都人の視点では絶対に小説を書けないので、そこで暮らしている人とは、ちょっとずれた視点にいる。
だから、僕の小説は「京都を書いている」のではなく、「京都というお皿に、自分の妄想を載せている」ということかもしれませんね。自分の妄想を「京都」に載せると、なんか様(さま)になる、と気づいただけであって、実際の京都とは距離があるんです。微妙なところですが、読者の皆さんにもぜひわかっていただきたい(笑)。
−−京都は、一定のイメージが広く共有されている土地だとも思うんです。「古都」や「寺社仏閣」のように、京都と聞いて、同じようなイメージが浮かびやすい。だからこそ、妄想を載せる「お皿」としても扱いやすいのかもしれませんね。
そうですね。妄想そのままではなく、京都というお皿に載せているからこそ、いろんな人たちに面白がってもらえる、読みやすいものになっているのかな。
森見さんの学生時代は「茶色っぽい」?
 鴨川沿いにあるシェアアトリエ『かもがわクリエイティブベース』に移動して、インタビューは続きます
鴨川沿いにあるシェアアトリエ『かもがわクリエイティブベース』に移動して、インタビューは続きます
−−森見さんの学生時代についてもう少し聞きたいのですが、思い出深い場所はありますか?
最初に浮かんでくるのは、鴨川の賀茂大橋のあたりですね。僕は大学生の最初の頃、北白川エリアに住んでいたんです。鴨川は京大生のテリトリーの一番端で、賀茂大橋を西に渡ったら同志社の人たちの縄張り、みたいなイメージ。実際そんなことはないんですけど(笑)。
その後、大学院生になって、河原町今出川のあたりに引っ越したんです。毎日、賀茂大橋を自転車で東へ渡って、大学のキャンパスへ通うようになりました。その時の景色が印象深いですね。橋の上から見える比叡山の景色が、四季折々で変わっていく。特に、雪が降って白くなった冬の比叡山を賀茂大橋から見た時に、「京都へ来たな」と感じたんです。
−−森見さんの作品に、よく賀茂大橋が出てくるなと思っていたんです。実際に思い出深い景色だったんですね。
小説のヒントにもなっていますね。ある夜、自転車で賀茂大橋を渡っていたら、雨が降ってきたんです。橋の欄干(らんかん)に一定間隔でランプがついているんですが、そのランプの傘の部分に蛾がたくさん避難していた。僕がその横を通りがかったら、蛾たちが驚いたのかいっせいに飛んできて……。
−−蛾の大群!『四畳半神話大系』のラストシーンですね! 実体験だからこそ、あの臨場感が。
 「鴨川デルタ」は京都の大学生の一部で呼ばれていた名称で、ごく局所的な言葉だそう
「鴨川デルタ」は京都の大学生の一部で呼ばれていた名称で、ごく局所的な言葉だそう
あとは新入生歓迎コンパの光景とか。僕の入ったクラブでも、毎年5〜6月ごろに鴨川デルタでコンパをやっていましたね。まあ、僕はそういう飲み会が好きではなかったんですけど。
−−その感じは、なんとなく小説からも伝わってきますね(笑)。
小説を読んで「京都で、さぞかし楽しい大学生活を送ったんだろう!」と思われることもあるんですが、そんなことはないんです。学生の頃なんて、ほとんどが悲しかったり、恥ずかしかったり、ずっとモヤモヤしていて、ごく稀に楽しいことがある。そんな学生生活でした。

−−学生時代を色に例えると、何色ですか? 新歓コンパで青春を謳歌している学生たちが白色だとすると。
黒色ではないですけど……やっぱり茶色っぽいのかなあ。当時の自分をリアルに思い起こしてみたら、怖くて仕方ない。「この先、自分はどうなっていくんだろう?」と不安に思っていました。勉強していたのもあまり興味のあることではなかったし、小説家にはなりたかったけれど、デビューもできなさそうだし。だから全然、当時には戻りたくないですね。
今だから落ち着いて振り返ることができますけど、当時は鴨川に行っても、物悲しい気持ちでした。でも、当時はヒリヒリしていたからこそ、綺麗なものは今よりもっと綺麗に見えていたと思います。だから、あの時に不安を抱えて見ていた鴨川のほうが絶対に綺麗だったでしょうね。

−−鴨川は森見さんと同じように、京都で青春時代を過ごしていた人にとって、鏡みたいな存在なのかもしれませんね。大人になって見ると、当時の自分を思い出すような。
そうかもしれませんね。あとは鴨川の上流と下流で、川岸の表情が変わるのも面白いなと思います。
三条大橋や四条大橋のあたりは「ハレ」の場だなって感じがする。等間隔で並ぶカップルも、なんだか祭り感があるというか、ちょっと気合いが入っている。
小説家になったばかりの頃は、四条大橋あたりのゴージャス感が好きで。そこに行くといつもワクワクして、想像力が刺激されました。だから『有頂天家族』という小説の最初で、劇場「南座」のてっぺんから女性の天狗が東華菜館の建物へ飛び移るシーンを書いたんです。
−−「弁天」ですね。あの場面はとても印象的でしたが、鴨川から生まれていたとは。
いっぽうで、鴨川沿いを賀茂大橋のあたりまで上がってくると、日常とハレの間の、ふわっとほぐれるような空間になる。人の過ごし方も変わりますね。
−−今日も本を読んでいたり、パンをかじっていたりする人がいて。多幸感のようなものを感じます。
大学生の頃は、「街に来た!」って感じで四条大橋のあたりに行くとテンションが上がっていました。でも、今は賀茂大橋のあたりのほうが楽というか、落ち着きますね。
困った時に出しがちな「鴨川」と「大文字」
 鴨川デルタでたまたま遭遇した、森見さんファンの女性
鴨川デルタでたまたま遭遇した、森見さんファンの女性
−−先ほど鴨川デルタで撮影をしていたら、『四畳半タイムマシンブルース』のヒロイン・明石さんの格好をしたファンの方と遭遇しましたね。こうして森見さんのファンが聖地巡りに京都へ来ているのだな、と感動しました。
嬉しいですよね。『四畳半タイムマシンブルース』の映画では、最後に夕暮れの鴨川デルタが出てくるんです。あの、もの寂しいような、甘いような光の感じがとてもリアルで、映画を観た時に感動したんですよ。自分が今まで見てきた鴨川デルタの空気感を、アニメですごく正確に描いてもらったなと思います。
 京都の劇団・ヨーロッパ企画の舞台『サマータイムマシン・ブルース』と、森見氏の小説『四畳半神話大系』がコラボレーションした『四畳半タイムマシンブルース』。2020年に小説が発表され、2022年にはアニメ版が配信、再編集を加えた劇場アニメ版が同年夏に公開された。
京都の劇団・ヨーロッパ企画の舞台『サマータイムマシン・ブルース』と、森見氏の小説『四畳半神話大系』がコラボレーションした『四畳半タイムマシンブルース』。2020年に小説が発表され、2022年にはアニメ版が配信、再編集を加えた劇場アニメ版が同年夏に公開された。
あとは僕、小説で困った時に鴨川を出しがちなんですよ。もしくは大文字(だいもんじ)の送り火。『四畳半神話大系』や『四畳半タイムマシンブルース』は鴨川が何度も出てきますし、今書いている小説のクライマックスには、大文字が出てきます。
−−小説の舞台として、すごく映えるということですか?
書きごたえのある、頼りになる舞台ってことなのかな。だから、もし鴨川や大文字の景色が変わってしまうと困りますよね。
なぜかというと、京都って、他の街に比べたら景色が変わりにくい。そこに、すごく助けられているんです。20年前に書いた『太陽の塔』も、今読んでもそこまで古臭く見えない。それは、京都のいろんな景色や建物や通りが、変わらずに今もあるからだと思うんですね。
−−東京の渋谷や新宿は、ランドマークも時代とともに変化していますよね。それに比べて、京都の街はあまり変化していない。
別に狙ったわけじゃないんですけどね。結果、助けられています。

−−温暖化や災害の増加など、環境の変化と鴨川も、けして無縁ではないと聞きます。
だから鴨川のこの景色が変わってしまうのは、小説家として困りますね。お願いだから、無くならないでほしい(笑)。
理屈じゃなく「鴨川べりは気持ちいいな」というのをみんなが共有していると、もし「なんか変だな」となっても、すぐわかりそうですし。それを通じて、今の自分の状態がわかるような存在が鴨川なのかもしれない。
−−かつての森見さんのような、茶色の青春を受け止める場所としても、鴨川は必要かもしれませんね。
鴨川は癒してくれる場所でもありましたからね。まあ、若い時のヒリヒリした状態だからこそ、書けるものもあります。僕も『四畳半タイムマシンブルース』で10年ぶりくらいに京都の大学生の話を書きましたけど、さすがにそろそろ大学生は厳しいなと。40歳も過ぎてますから。
−−ちなみに新作のご予定は?
「スランプ」がテーマの小説です。コロナの間にそんなテーマの小説を書いちゃったから、なかなか大変で。それがやっと完成したので、さらに次の作品を考えているところですね。
−−森見さんの新作を読めるのが楽しみです。今日はありがとうございました!
おわりに
「鴨川べりは気持ちいい。一体なぜなんだろう?」そんな編集部メンバーの問いからはじまった、今回の企画。街のすぐそばに自然があり、その自然がつくりだす「街の余白」のような空間が、心を解放し、その時々の自分と向き合わせてくれる……。気持ちよさは、きっとそんなところから生まれているのではないでしょうか。
私もまた、17歳のときに読んだ『太陽の塔』以来、森見さんの小説に大きな影響を受けてきたひとり。今回の取材にあたって過去作を読み返した際、当時の自分のヒリヒリとしていた気持ちが一気に蘇りました。と同時に、年を重ねたからこその新しい発見や読後感も。私にとっての森見作品は、森見さんにとっての鴨川のような、向き合うことで「今の自分の状態がわかる存在」とも言えるかもしれません。
そして森見さんの「妄想」に救われてきたからこそ、その妄想を産んだ京都の風景が、鴨川が変わらないでほしい、と感じた取材でした。

取材協力:かもがわクリエイティブベース
小説家
1979年、奈良県生れ。京都大学農学部大学院修士課程修了。2003年、『太陽の塔』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、作家デビュー。2007年、『夜は短し歩けよ乙女』で山本周五郎賞を受賞。2010年『ペンギン・ハイウェイ』で日本SF大賞を受賞する。ほかの著書に『四畳半神話大系』『きつねのはなし』『新釈 走れメロス 他四篇』『有頂天家族』『美女と竹林』『恋文の技術』『宵山万華鏡』『四畳半王国見聞録』『聖なる怠け者の冒険』『有頂天家族 二代目の帰朝』『夜行』『太陽と乙女』『熱帯』がある。 森見 登美彦の記事一覧へ >
取材・執筆
取材・執筆