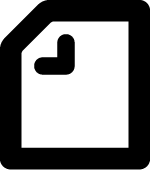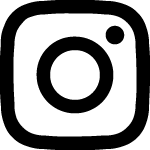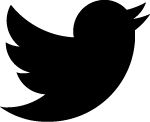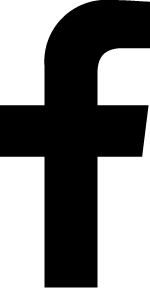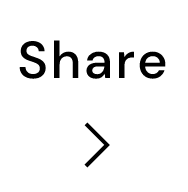ライフスタイル転換のための仕掛け=プロジェクト
脱炭素に貢献するけど、脱炭素だけではない。
プロジェクトを通じて、
楽しい、かっこいい、ワクワクする魅力的な「変化」が起こっています。
今回は、「脱炭素ツーリズムHUB創設プロジェクト」を始めた(株)Slow Innovation 代表取締役 野村恭彦さん(以下、野村さん)と、コーディネーターの(株)JTB 京都支店 藤本直樹さん(以下、藤本さん)に、プロジェクトに対する想いについてお話を伺いました。
「脱炭素ツーリズムHUB創設プロジェクト」の取組内容は、こちら(https://doyoukyoto2050.city.kyoto.lg.jp/projects/tourism-hub/)をご覧ください!
京創ミーティングに参加したきっかけ
野村さん:当時、京都市のSDGs担当からの相談や、社会ビジネスに取り組みたいクライアントがいたこともあり、京都でSDGsツーリズムをやろうと検討していたところに、地球温暖化対策室からのお誘いで参画しました。もともとツーリズムには関心があって、SDGsと脱炭素の文脈で間を取って、“スローツーリズム”に至りました。
プロジェクトを進めていく上での懸念点等
野村さん:僕らは基本的にコンサルティングの会社で、クライアントがやりたいことを手伝う、というスタンスです。要するに、お金がもらえることが分かっているので、既にビジネスが成立しています。一方で、今回のプロジェクトは、自分達がどこまでやってもリターンが得られるか分からないことに挑戦するという点で、とても勇気が必要でした。
それをやるためには、やはり協働の相手が熱心ではないと続きません。自分達だけで続けていたら、孤独な作業になっていたと思います。そういう意味では、2050京創ミーティングの事務局の皆さんが本当に仲間として伴走していただいた点が心強かったです。家族みたいな、定期的に集まる親戚のようなあったかい関係ができました。特にカーボンニュートラルは短期的にベネフィットのある取組ではないため、メリットを超えた協働関係が必要だと強く思います。

(写真:スロージャーニーから)
- ビジョン策定のチームメンバーになっていただくなど、どちらかというと市役所の「相談役」という立場での関わりが多かったと思いますが、今回、プロジェクトを推進する「プレーヤー」として取り組むきっかけはあったのでしょうか?
野村さん:4年前に京都に移住してきたときから、もともとプレーヤーとして自主事業をやりたい、という思いがありました。とはいえ、クライアントワークの方を優先してしまい、当時はやれる範囲でやる、という形になっていました。ところが、京都市の脱炭素ライフスタイル推進事業のプロジェクトとしてやってみませんか?と声をかけていただき、これは一生懸命やれるいい機会だな、と。ここで京都市からのサポートを受けながら自分達の事業として立ち上げることができたらいいなと思いました。そういう意味では、新規事業に取り組むきっかけを作ってもらえました。

(写真:野村さん)
プロジェクトを進めていくうえで事務局と共に取り組んでみて
野村さん:プロジェクトを通じて、市民が無理なく脱炭素ライフスタイルに参加できる仕掛けをつくりたいと考えています。本業との関係から、企業へのアプローチは比較的簡単ですが、地域へのアプローチのハードルが高いと感じていました。僕らが今から地域に根差した活動を一歩踏み出していくうえでも、普段から地域とつながりがある事務局などを通じて、地域に住んでいる方々へアプローチできる点は有難かったですね。協働することによって、商店街をハブとして色々な人たちがつながる場を作ることが、僕らが今やりたかったことです。
-コーディネーターの藤本さんには、他都市や海外における環境に配慮したツーリズムの事例紹介や、専門的な立場からのアドバイスをいただき、プロジェクトの取組を支えていただきました。
藤本さん:これまでサステナブルツーリズムというと、どうしても観光課題が前面に出てしまっていましたが、ツーリズムがもたらす「豊かさ」もあると考えていました。カーボンニュートラルの文脈で語ることで、観光課題というセクションに留まった課題ではなく、もっと大きな課題へアプローチできること、課題の切り口をずらすことができた点が良かったと感じています。また、カーボンニュートラルやSDGsといったグローバルな課題を主軸に「スローツーリズム(野村さん提唱)」の在り方を模索した結果、最終的には地域の暮らしや文化に根差した観光=ローカルに収束していった。その展開がとても興味深いと感じています。

(写真:スロージャーニーから)
スロージャーニーの参加者の反応は
野村さん:効率的に観光地を回る「ファストツーリズム」ではなく、継続的な参加や地域とのゆるやかなつながりを生む「スローツーリズム」を目指し、京都の脱炭素な取組を体験できる「スロージャーニー」を開催しています。
何か月も前に参加してくれた方が、今でもご自宅でスロージャーニーの話をしている、と伺いました。行動が変わるというより、その人の考え方の中にそういう文化とか脱炭素とか、そういったものに取り組むライフスタイルがインストールされた、ということが多いと感じています。座学では絶対起きないことですよね。
スロージャーニーへは、もともと脱炭素に関心のある人が来ているので、参加したことで脱炭素アクションが進んだか、と言われると、いまいち差分はないかもしれません。ですが、参加者の多くは「自分1人でできること」に取り組んでいる人が多かったのが、スロージャーニーに参加することで、「他の人と一緒にできることを広げる」という行動(マインド)の変化が見られます。これは、一人では解決できない課題である「カーボンニュートラル」の実現に向けて、必要不可欠である「協働」にもつながると思います。
また、スロージャーニー自体も、ビジョン策定のメンバーでもある養徳院の横江さんと一緒にプログラムを作ったり、「菜食対応のメニューを提供する店舗の見える化プロジェクト」のメンバーである合同会社KYOTOVEGANの玉木さんとビーガンジャーニーを考えたり、スロージャーニー自体が何かをつくる協働の場になっていますね。

(写真:スロージャーニーから)
「2050京創プラットフォーム」に寄せる期待
藤本さん:一人一人の自発性ですとか、仏教的に言うと自然(じねん)みたいな、自分があるままである状態であって、その人たちが協働することが豊かさにつながるという、すごくボトムアップのやり方やアプローチを期待したいですね。一人一人のありたい姿っていうのを評価するような新しい評価指標とか、そういう話をどんどんしていくことが、結果的に協働することにつながり、豊かさという成果につながると思います。
野村さん:この京都の市役所っぽくないユニークな脱炭素の取組は、すごく面白いと思いますし、プラットフォームとしてどんどん発信を頑張ってほしいですね。「2050京創プラットフォーム」の取組が市民レベルにまで広がることを期待します。
(インタビューは2024年10月に実施しました。)
地域イノベーションのプロデュース・コンサルティング等
自治体の市民協働・企業協創・政策形成とつなげることで、各地域に生きた「市民協働イノベーションエコシステム」を構築することで、「地域から日本を変える」ことを目指して2019年に創設。「人と人との関係性を大切にした新しい社会の形」を地域のステークホルダーとともに「ゆっくりと」進めています。 Slow Innovation株式会社の記事一覧へ >